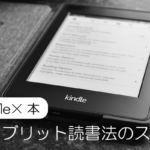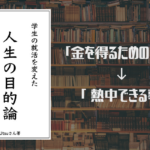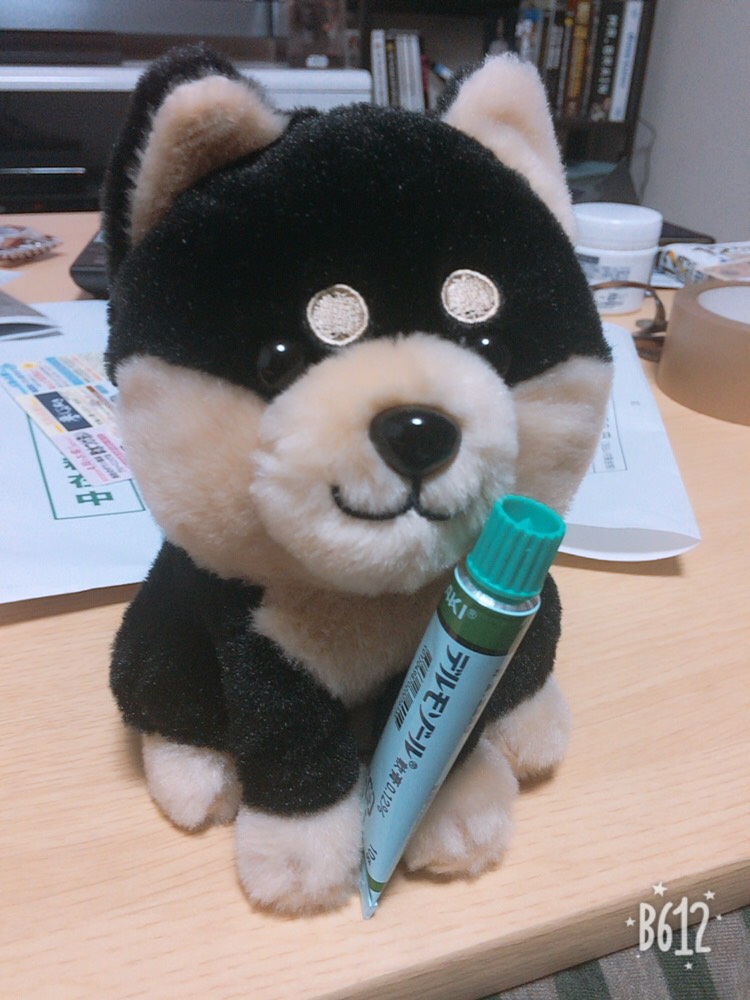こんにちは。ともなり@ライフデバッカーです。

仕事辞めたいな~
誰しもこのように考えた経験はあるのではないでしょうか?
働くということは、必ず身体的疲労や精神的ストレスを感じるものです。
特に精神的なストレスは、働く上で大きな問題です。
疲労は、ゆっくり休めば回復しますが、精神的な部分はそうはいきません。
- 今日までに資料を作成しないと、でも電話対応もしなければ・・・
- 自分の失敗ではないけど、取引先に謝罪に行かなければ・・・
- 「口うるさい上司へ大事な商談の報告をしなければ・・・
このように、私たちは常にプレッシャーに直面し、ストレスを感じています。
私もSEという職業を日々やっていて、ストレスを感じることがよくあります。
忙しい時は、深夜や休日まで仕事することがあります。
また、夜でも休みの日でもも、電話がかかってきたら対応しなければならない時もあります。
海外へ一人旅に行っていた時でさえ、午前4時頃に電話で叩き起こされたこともありました。
そんな時は、「やってらんね~」と思ってしまいます。
これまで、ストレスに押しつぶされて部署を異動したり、精神的に病んでしまって会社に来なくなってしまった同僚も見てきました。
しかし、私はというと、客観的に見て残業も多く、プレッシャーのかかる業務も複数並行して行っていますが、仕事へ支障がでるほどストレスは感じません。
それは、「ストレスを感じないマインド」が備わっていて、しっかり機能しているからです。
今回は、これまでの経験からストレスに有効だった考え方を紹介したいと思います。![]()
仕事を辞めたいと思う原因

仕事を辞めたいと感じるのは、どのようなタイミングでしょうか?
ずばりストレスを感じる時です。
仕事量が膨大で締め切りに追われているシーンもあるでしょう。
重要な仕事をまかされて周囲の期待を背負うというシーンもあるでしょう。
ですが、こういったストレスは一時的なもので、場合によってはモチベーションがあがったりと、プラスのストレスになる場合もあります。
一番のストレスはやはり人間関係ではないでしょうか?
例えば、
- 他人から嫌われるのが恐くて、人の評価を気にしすぎている。
- 失敗の原因は、他者ではなく、自分だと自責してしまう。
- 今まで築き上げた環境、人間関係を失うことを恐れてしまう。
のような考えをしてしまうことはないでしょうか?
事実、厚生労働省の調査(労働者健康状況調査 2012年)によれば、ストレスを感じる時の理由は、以下の通り「人間関係」が最も多いです。
最近よく関連書籍がでている「アドラー心理学」でも、悩みのすべては「人間関係」だと断言しています。
では、こういったストレスを回避する方法はあるでしょうか?
以下に私が実践しているストレスを感じているなと思ったときに実践している考え方を解説します。
仕事を辞めたいと思った時の対処法
「今こそ鈍感力だな!」と考える

当時、小泉前首相が阿部首相へ「鈍感力」というキーワードを使って以下のようなメッセージを送りました。
これにより、書籍はベストセラー、2007年の流行語大賞のベストテンに入賞するほど有名なりました。
「鈍感」は通常あまりポジティブな意味合いでは使われません。
一方、対義語である「感覚が鋭いこと、素早い」の意味がある「敏感」や「鋭敏」なんかがポジティブなイメージで使われいます。
しかし、どうでしょうか。
ストレスを誘発するストレッサーに対しては、鈍感であるべきなのです。
例えば、仕事でミスをして上司に叱られたとします。こういった時に、

上司にも嫌われたんじゃないかな
と落ち込んで、このことを2、3日引きずり仕事も手につかないようなナイーブで敏感な人がいるとします。
その一方で、

こっちはもう十分反省して、再発防止策も考えたんだから、ごちゃごちゃうるせーよ。
時間かえせや。偉そうに言ってるあんたも若い時はミスしただろうが。
と切り替えられる鈍さをもった人のほうがストレスは少ないのです。
ネガティブな出来事に対して、深刻に考えるのではなく、
「まぁ大したことじゃない」「なんとかなる」と考えて自分のやるべきことを淡々と進めればいいのです。
人からの評価も気にしてはいけません。
誰もあなたのことを、それほど興味を持って見てはいません。
仮に上司から評価されるなんてことがあれば、

仮に会社が倒産したら、あなたはただのおっさんだろ?
と考えればいいんです。
人からの評価は、そこまで真面目に受け止める必要はありません。
それは、その人の主観の話で不変的、絶対的なものではありません。
誰かに嫌われたとしても、それは自然なことです。全世界の人々に好かれるなんで不可能なことです。
自分の大切な人(家族、恋人、友人)といい関係であればいいんですよ!
課題の分離をする。

先ほども少し紹介した「アドラー心理学」を扱った「嫌われる勇気」でも登場する「課題の分離」は有効な考え方です。
例えば、大事な商談があり、自分がその商談の担当だったとします。
いろんな部署に確認をとり、提案書、見積もりをまとめて上司の承認を得て、お客さんに提示します。しかし結果は他社に敗退・・・。
関係者で敗退の原因分析会を行うなんて話になってしまった。
このような時に、

と、真面目な方は考えてストレスを感じてしまいます。
しかし、自分がやるべきことをやった結果がそうであれば自分を責める必要なんてないのです。
この場合、課題は会社にあると考えます。
- もっと会社としていい提案をできなかったのか?
- 原価を下げれなかったのか?
- 商談の体制をもっと強化しておくべきだったか?
もはや自分でどうにかできる範囲を超えています。
自分が取り組むべき課題と、そうでない課題を分離して考えることが重要です。
また、こいったケースで犯人捜しのような会議が行われるケースがありますが、あまり間に受けないほうがよいです。
出来事に根本的な原因なんてありません。ただの妥協点を関係者の合意のもと探っているだけです。
ロシアンルーレットが行われているんだという気持ちで臨めば十分です。
「あの人」の期待を満たすために生きてはいけない――
【対人関係の悩み、人生の悩みを100%消し去る〝勇気〟の対話篇】世界的にはフロイト、ユングと並ぶ心理学界の三大巨匠とされながら、日本国内では無名に近い存在のアルフレッド・アドラー。
「トラウマ」の存在を否定したうえで、「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と断言し、
対人関係を改善していくための具体的な方策を提示していくアドラー心理学は、
現代の日本にこそ必要な思想だと思われます。本書では平易かつドラマチックにアドラーの教えを伝えるため、
哲学者と青年の対話篇形式によってその思想を解き明かしていきます。
対人関係に悩み、人生に悩むすべての人に贈る、「まったくあたらしい古典」です。
機会均等の法則を意識してみる

私たちは何かを体験している時、同時に何かの体験をするといった機会を失っています。
例えば、恋人がいない時は恋人が欲しいと考えます。
しかし、恋人ができてみると一人の時間が欲しいと考えることがあると思います。
つまり、恋人ができたことで、恋人がいなかった時に一人で自由にできていた趣味だったり、友人との付き合いという機会を失っているといえるのです。
仕事でも同じです。
Aという企業に就職した場合、同時にBという企業で働く機会を失っています。
今が最善とは限らないということです。
もしかしたら、自分にもっとあった仕事があるかもしれませんし、実は今の生活が自分の価値観にあっていないかもしれません。
- 今の人間関係を壊さないように、自分の意見は抑えて周りに合わせよう
- 辛いけど会社に居続けるためには、我慢するしかない
- 自分がいないと仕事が回らない、辞めたら迷惑がかかる
このように、今の環境に固執してストレスを感じ続けるのは、人生全体から見てハッピーなことでしょうか?

という気持ちを持っていれば、ストレスから逃れられます。
もちろん環境の変化もストレスです。
見知らぬ場所や仕事、人間関係に急に放り込まれたら誰でも不安です。
しかし、これまでも同じような経験をしているはずです。
高校を卒業して大学に入った時、大学から就職した時、仕事で勤務地が変わった時。
きっとその時は不安だったと思いますが、乗り越えてこれているはずです。
常に私たちには、失っているもう一方の機会がある。
「他にも道はある」と考えましょう。
仕事を辞めたいと思った時の対処法のまとめ
いかがでしょうか?同じような考え方をしている方もすでにいると思います。
また、いい加減な考え方と思われる方もいるでしょう。
「仕事行きたくないな~」「仕事辞めたいな~」なんて思った時に、まずは思い出してみてもらえればと思います。
明日の仕事に向けて何かヒントになればと思います。
本記事で紹介した書籍もぜひ読んでみてください。
「あの人」の期待を満たすために生きてはいけない――
【対人関係の悩み、人生の悩みを100%消し去る〝勇気〟の対話篇】世界的にはフロイト、ユングと並ぶ心理学界の三大巨匠とされながら、日本国内では無名に近い存在のアルフレッド・アドラー。
「トラウマ」の存在を否定したうえで、「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と断言し、
対人関係を改善していくための具体的な方策を提示していくアドラー心理学は、
現代の日本にこそ必要な思想だと思われます。本書では平易かつドラマチックにアドラーの教えを伝えるため、
哲学者と青年の対話篇形式によってその思想を解き明かしていきます。
対人関係に悩み、人生に悩むすべての人に贈る、「まったくあたらしい古典」です。
どちらもKindleで読むことができます。
Kindleについては、以下の記事を読んでみてください。
それでは!